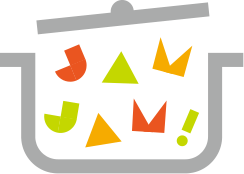【 engawa young academy 】 メンターインタビュー NTT西日本篇
#インタビュー

2020年10月より、engawa KYOTOにて始まった多業種合同インターンプログラムengawa young academy 2020(以下、eya)。参加企業のメンターの皆様から、eyaに参加されての感想や参加された理由、また学生に知ってほしい企業の新たな一面などを伝えるために、各社インタビューを行います。第1回目は、NTT西日本の谷村さん、石田さんにお話を伺いました。
写真左)西日本電信電話株式会社 人事部 人事第一部門 谷村 祥太さん
写真右)同社 ビジネスデザイン部 スマートデザイン第3部門 石田 裕紀さん
所属は、取材:2020年11月当時のものです。
−eya、初日を終えての率直な感想はいかがでしょうか?
谷村さん:一言で楽しかったなと思っています。学生の皆さんが優秀で、皆さんへの興味・関心を刺激されたところがその源泉でした。石田とも喋ったんですけど、僕も学生時代に起業したり、石田も団体の主催をやったりしましたが、その昔のチャレンジ精神を学生から改めて教わったなと思いました。
石田さん:起業するとか団体立ち上げるとかって、僕の世代では比較的レアな経験だったように思います。けれどeyaに参加している学生は、起業や団体運営なんかは当然経験済みで、ICTやSNSを使いこなしながら個人としての影響力も高い。そういう経験を持った人の数が、僕らの時代とは比較にならないな、みたいな会話をしていました。
−学生時代の活動におけるラインが上がっているように感じます。僕も学生の自己紹介の時間、一定層の学生を集めているとはいえ、こんな時代なんだ、と思ったところでした。
石田さん:学生の自己紹介の時間は驚きの連続でした。僕らの世代のプレゼンって、オーディエンスは静かに聴くじゃないですか。でも今の世代はどんどんチャットで盛り上げるし、プレゼンターもそれを取り上げる。静かに聞くことがマナーって感じる世代と、チャットとか使って盛り上げてあげるのがマナーって感じる世代と、人をリスペクトしようっていう方向性は同じなのに、アプローチは全く逆だな、と。
谷村さん:たぶんインスタライブとか、webのライブ放送でも番組しながらコメントするのが当たり前じゃないですか。ビジネスの場にも、そういうのがこれからおそらく出てくるんだろうなって感じですね。
−では、そういった学生を前に、谷村さんにメンタードラフト※をしていただいたのですが、その感想を聞かせてください。
※メンターが企業名を隠して、学生に対して自己紹介プレゼン。学生が希望するメンターを指名するプログラム
谷村さん:採用担当として、学生の立場に立ててよかったなって思います。あんな心持ち、緊張感、本気度を持って、学生の皆さんが面談に来ているんだろうなって思いました。採用の場面では学生側に求めていることなので、今後にもつながるいい機会だったなって思います。
−企業側のeyaへの本気度を伝える上で、あの緊張感が学生側にもよい刺激になっていると思います。ではここから、御社のことについてお伺いしていきます。御社は今、学生からどういう企業イメージを持たれていると思いますか?
谷村さん:固定電話や光インターネット回線といった通信ネットワークのみを扱う単一事業者のイメージが強いのではないかと思います。
−では、御社の実際の姿を知らない学生へ、実はこんな企業なんです、という、知られてないけど伝えたいこと、紹介して頂けますか?
谷村さん:ネットワーク事業が根幹で中心なんですけど、通信関連で言うとデータセンターとかセキュリティ、コンタクトセンター(顧客からのお問い合わせ・お申込み対応窓口機能)のソリューションもやっていたりします。通信以外の、あまりイメージがないのかなというところでは、不動産ビジネスとかドローンビジネス、あとはインターネットラジオとか電子コミックといったコンテンツ系のビジネスもやっています。例えば、ドラマ「私の家政婦ナギサさん」(2020年9月:TV放送)は、NTTソルマーレというグループ会社の電子コミックのコンテンツです。単一事業でネットワーク、インフラっていうと守るイメージが強いと思うんですけど、ネットワーク部分でのチャレンジはもちろん、多角化展開へのチャレンジもぜひ知ってもらえたいです。
−確かに、ネットワーク以外でそこまで多角化にチャレンジされていることは、なかなか伝わっていないかと思います。ネットワーク以外の多角化へのチャレンジですが、そこに踏み出すタイミング、きっかけがあったのでしょうか?
谷村さん:固定電話はもう使われなくなってきている、という現状と、光インターネットも普及率を人口ベースで100%に近づいていて、NTT西日本の光サービスのシェアはエリアにもよりますが、その内の6割、7割というレベルでの争いになっているんです。そういったことを考えると、他の競争分野に人もお金も使わないと、固定電話の減収をカバーできない状況で、そこに対してどうチャレンジしていくかっていうのが今のうちの会社の命題ですね。
−多角化展開を図るにあたって、何かしら基準はあるのでしょうか?
谷村さん:1つあるのは、地域の社会課題にコミットできるかみたいなところで、「ビタ活」と言っている取り組みがあります。「ソーシャルICTパイオニア」(ICT:Information and Communication Technology(情報通信技術))として、地域を元気にする“ビタミン”のような会社になろう、という意味です。
NTT西日本のソーシャルICTパイオニアの事例
https://www.ntt-west.co.jp/brand/regional/
石田さん:自社のアセット、ノウハウがしっかり活かしながら、今、谷村が申し上げた、特にその中でも社会課題とか地域創生、ワールドワイドというより地域密着型の課題解決ができる事業をつくっていこうっていう、軸がありますね。
谷村さん:日本の数ある企業の中でもめずらしい会社だと思います。市場として、世界や首都圏という選択肢を取りづらく、かつ47都道府県のうち30府県をエリアカバーする多くの地域をマーケットとして持っている会社。地域の発展が当社事業の発展であり、その地域が広いという非常に特異な会社なのではないかと思っています。
−なるほど、先進の技術とそのノウハウを、西日本という広いエリアにある様々な地域の特性、課題に合わせてどういかしていくか、というポジションは、確かに独自性がありますね。この取り組みが一つの形、ビジョンとなっているのが、スマート10x(エックス)、ということでしょうか。
谷村さん:そうですね。ICT(情報通信技術)をコアに、B to B to Xと表現している ますが、例えば顧客企業が持っている事業ノウハウと弊社が持っているICTを掛け合わせて、顧客企業の先にいるお客様に対して価値提供をする、その際のスマートの部分を僕たちが担う、ということです。例えばアグリだったり、エデュケーションでのギガスクール支援やローカル5Gを使ったスマートファクトリーとしての工場自動化、スマート防災としての水門陸閘の自動化など、スマート10xであげている領域を通じて地域を元気にするという価値観で展開していくイメージを持っていただけると近いと思います。

※スマート10xについて
https://www.ntt-west.co.jp/business/n-colle/smart10x/
石田さん:先ほどの、新規事業展開における基準の3つめを、今、スマート10xのことを話しながら思い出したんですけど、まだ取り組みの途中ですが、単なるICT、ITのシステムを作って終わりじゃなくて、それを使って既存の業界のビジネスプロジェクトを変えるとか、オペレーションを変革するとか、そこまで食い込まないと、本当の意味で顧客の課題解決になる時代じゃないよねっていう課題感がすごくあります。
−スマート10xの裏には、そういう課題感があるんですね。石田さんが所属しているビジネスデザイン部が、スマート10xの中心を担われていると聞いているのですが、具体的に石田さんはどのような事業をやられているのでしょうか?
石田さん:具体的には、インフラ事業者 向けにICTを使ってDX化を推進していく、それによって新しい事業のオペレーションのやり方を構築する、ということに取り組んでいます。例えば、スマートメーターという商材があります。ガスや電力、水道の事業には検針業務が必要で、これを無線回線で遠隔化・自動化しましょうというものです。
1つのメーターが持つデータ量は少ない一方で、対象となるメーターの数が何百万台と存在します。さらにメーターは、家の奥の電気がない場所についていたりすることが多く、取り換えも数年に一度だけなので、スマートメーターは電池稼働で数年間稼働する必要があります。つまり小容量でもいいから、出来るだけ省電力で通信できるIoTデバイスとネットワークが必要なんです。 弊社のグループ会社であるNTTネオメイトからは既に、LoRaWAN®(ローラワン)というLPWAネットワーク(省電力を特徴としたネットワークの総称)を提供しています。これを使って、スマートメーターを遠隔化するだけでなく、さらに付加価値を作れないか検討をしていて、例えば、リアルタイムでデータが取れるため、そこから水の量が見えてくると、断水・漏水の発生箇所を推定できないかとか、高齢者の方の見守り、あと水の需要予測をより精緻化することで水道事業そのものをより最適経営に変えていく、そういうことを目指せたら、という考えでやってます。このように、LoRaWAN®を軸として、IoTデバイスからネットワーク、データ収集サーバまでを含めたトータルソリューションの提供を目指し、今まさに商品開発からプライマリーユーザの開拓まで、新規事業のすべてのイベントに関わりながら、プロジェクトを進めています。
谷村さん:ちなみに、福岡市では、このLoRaWAN®を産業振興という目的に活用するという試みを行っています。
Fukuoka City LoRaWAN®の取り組みについて
https://www.ntt-west.co.jp/ict/casestudy/lpwa_fukuoka.html
−単純に通信って、高速・大容量になればいいかっていうことでもないんですね。ついそっちの方に目が行きがちなので、とても面白い切り口です。もう少し聞きたいところなのですが、、、次の質問にうつらせて頂きます。御社の採用に関してですが、御社が重視している指針や取り組みを教えてください。
谷村さん:当社が最も大切にしていることは、「多様な採用」です。学歴や経験、スキルに囚われない、幅の広い採用活動をめざしています。インターンについては、学生に成長環境を提供すること、採用としては時間・場所・手法を幅広く構えて、多くの学生に会うことを一番に考えています。
−御社が行うインターンでは、学生にどのような成長環境を提供してらっしゃるのでしょうか。
谷村さん:インターンの主題は「10年後の未来の社会を考えましょう」というもので、eyaにも似ていて最大2ヶ月に4日間しか集まらないんですけど、定期的にピックアップした新聞記事やPEST分析、3C分析などといったビジネスフレームなどを弊社のビジネスチャットツールを使って送ったりして、学生の一般的な教養知識を深めてもらうことを考えています。
−お伺いするに、正直準備が大変なインターンだと思うんですけど、なぜそのような取り組みをされるのでしょうか?
谷村さん:根本的な思想として、限られたマーケットの中で各社が競い合って人を取り合うって不毛だなと思ってます。そうじゃなくて、マーケット自体の質を向上させれば、もちろんその数に限りはあるんですけど、勝った負けたじゃなくて全員ハッピーになれるんじゃないか、という思想の元で、今のインターンを提供しています。
−まさに、eyaも同じ思想です。そのようなインターンをされている中で、御社が求めている人材像はどのようなものでしょうか?
谷村さん:一言でいうと、「変われるand変えられる人材」です。「(変わることを受け入れる)素直さ」、「(変わろうとする)ちょっとした勇気」、「(変わるための努力を)やり切る力」、「(周りを変える)影響力」が必要だと考えています。まず変わることを受け入れる素直さって必要だなっていうこと。変わるときにかかる精神的コストを乗り越えられる人。変わろうとする勇気を持っているか。で、変わろうとすると小さなことから1つずつ達成しないといけないんですが、それらを最後までやり切れるかっていうところ。最後は、基本的にビジネスってチームで動いたり、お客様がいたり、複数の人と働くので、周りの人たちを感化していける影響力を持っている人です。
−そういった人材にアプローチする上で、課題と感じているところを教えてください。
谷村さん:心底、当社のインターンは学生の成長に寄与すると思っていますので、良くも悪くも「NTT西日本」という看板が大きいことで、選択肢に入らない学生がいるのではないかと思っています。自己成長の場としてもっと多くの学生に参加してほしいと思っています。採用としても「NTT西日本」から想起されるイメージが固定化されてしまっている部分があると思うので、それをどう多様なものに変えていくかが課題です。
−NTTが強いブランドだけに、ハードルが高い課題ですね。eyaの中で、学生に対してそのイメージを崩すサポートができればうれしいです。では、社内で多様な人材を育成するために、社員への成長機会の提供などに関する取り組みがあれば、教えてください。
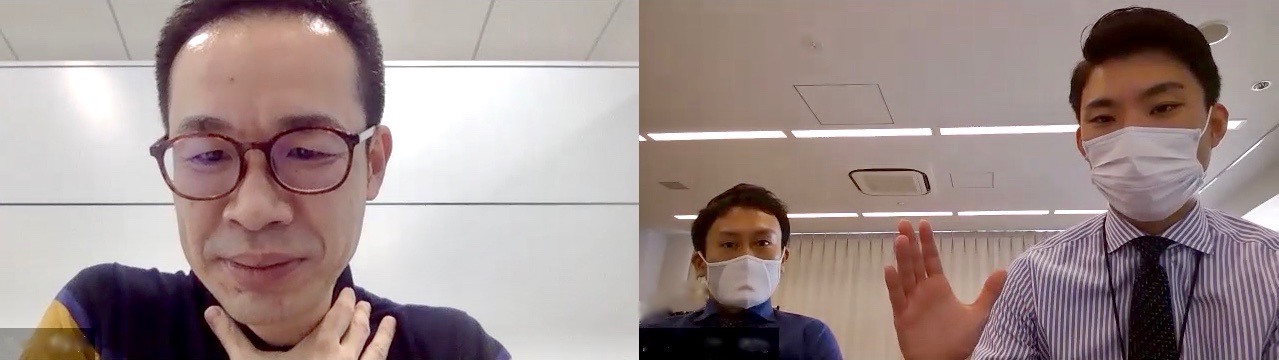
オンライン取材の様子
左)インタビュアー: 電通 京都BAC engawa young academy 事務局 眞竹 広嗣
谷村さん:当社は人材開発ビジョンとして「個の自立」を掲げています。そのため、1,000を超える研修や通信教材を準備し、画一的な人材の育成ではなく、社員自らが選び取って成長していくことのできる環境を整えています。人事運用面でいうと、リーダーやマネージャーといったポジションに若いうちからつかせようとする傾向が強くなっているのがここ最近の当社の動きです。
−石田さんは、そういった社内制度を活用されてMBAを取得されたと思うのですが、現在のビジネスデザイン部に所属まで、どのようなキャリアなのでしょうか?
石田さん:元々僕は、島根県で営業をやった後に、経営企画部に配属になりました。その時に、東京と いう日本で一番おいしいマーケットがない西日本、競争も苛烈、だから付加価値の高いサービスや通信以外の新規事業っていうのも作っていかなくちゃいけない、っていう経営課題を持っている会社って特殊だな、と思ったんです。自分が経営企画という立場からどう取り組むかを考えたとき、この特殊な経営について議論をしたり、知恵を授けてくれる仲間を作るというのはいいかもと思って興味を持ったのがMBAだったんです。で、ありがたいことに社内の人事制度で送り出してくれて、帰ってきたら行くとき以上に新規事業を何とかして作ってくんだという課題が会社の中で大きくなっていて、その流れで今の部に着任しました。
−ご自身の変化と企業の変化がシンクロしての現在のポジションに着かれたんですね。では、ここからeyaのことについてお伺いしたいと思います。御社は企業の変化がさらに加速している環境下だと思うのですが、その中でeyaに参加されたその理由、意義、メリットなどを教えてください。
谷村さん:世の中的に「優秀」と言われる人材がどういった人材なのか、を知り、当社の母集団との差分を知ることができれば、と思いました。
−では、ご自身として、メンターとして参加する意義や期待、メリットなどはいかがでしょうか?
石田さん:一つはコーチングや育成という観点で自身の成長がある点。参加している社会人の方は、「今プロジェクトをガンガン引っ張っている人」が多いと思うけれど、eyaでは「学生が主体的にプロジェクトを動かしていくことを如何にフォローするか」だったりするので、ある意味では今のキャリアの先のことに取り組めているようにも思います。
−eyaは、異業種による人材育成への取り組みになりますが、そのような取り組みに対してどのような効果、刺激を期待されますか?
谷村さん:学生の個の能力を上げることもできれば、と思っていますが、多くの企業が集まるからこそ伝えることのできる、社会を構造的に理解できる力や一つの物事を多様な角度からとらえる力を一緒に蓄えていけたらな、と感じています。
石田さん:参加されるすべての人にとっての変化や成長といった飛躍のきっかけになれば良いと思っています。自分にとっては、今の①若い世代、②同世代の異業種から、視点や視座の違い、モチベーションの違いなどを学べることを期待しています。
−eyaの学生たちと接して、感じたこと、期待することはどのようなことでしょうか?
谷村さん:自分から動いているな、と思っていますし、人事としては、このような学生に対して強みを伸ばしてもらえるようなパーソナライズな育成環境をどう提供するか、をすごく考えさせられます。
石田さん:今の良さを持ったまま、自由に社会に羽ばたいてほしい。みな素晴らしい能力や経歴を持っているのに、人間的にも素晴らしいので、ぜひeyaや今後色んな場で出会う人たちを大切にして、それぞれの人生を楽しんでほしい。
−メンターとしてeyaの学生たちに伝えたいことや意気込みをお願いします。
谷村さん:皆さんとともに学び、成長できればと思っています!その中で自分の今までの経験から伝えられることは全力で皆さんにお伝えしますし、皆さんからもたくさんの刺激を受けられればうれしいです!最後は戦友になれるように全力で取り組みましょう!
石田さん:学生のみなさんに負けないよう、一生懸命取り組みたいと思います。いっしょにeyaを楽しみましょう!