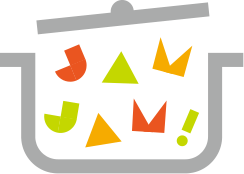【engawa young academy】 メンターインタビュー 電通篇
2021年10月より、engawa KYOTO REMOTEにて始まった多業種合同インターンプログラムengawa young academy 2021(以下、eya)。参加企業のメンターの皆様から、eyaに参加されての感想や参加された理由、また学生に知ってほしい企業の新たな一面などを伝えるために、各社インタビューを行います。第2回目は、DAIKINの西川さん、伊藤さんにお話を伺いました。 第1回 ヤマト運輸様 メンターインタビューは こちら 第2回 DAIKIN様 メンターインタビューは こちら 第3回 積水ハウス様 メンターインタビューは こちら 2021年10月より、engawa KYOTOにて始まった多業種合同インターンプログラムengawa young academy 2021(以下、eya)。参加企業のメンターの皆様から、eyaに参加されての感想や参加された理由、また学生に知ってほしい企業の新たな一面などを伝えるために、各社インタビューを行います。第4回目は、電通の湊さん、工藤さんにお話を伺いました。 写真右)株式会社電通 京都ビジネスアクセラレーションセンター 湊 康明さん 写真左)株式会社電通 中部BC局 ビジネスデザイン部 工藤 永人さん 所属は、取材:2021年11月当時のものです。 ― 参加学生が、京都、大阪、広島、韓国に留学中の学生まで。 インタビュアー眞竹(以下、眞竹) :初日、2日目を終えての率直な感想を教えて頂けますか?湊さん、いかがでしょうか? 湊さん :私は、今年で電通のメンターとして、2年目を務めさせていただいておりますが、昨年と比較して変わった事は、コロナ禍による大きな社会変化が起こっている事が普通になってきているという事ですね。デジタルツールを使いこなすことは勿論、私のチームには、現在の居住地が、京都、大阪の人もいれば、広島の人も、韓国に留学中の人もいますよね。電通のメンターも、そもそも大阪と、名古屋ですし(笑)。それが普通で、その前提で特にこのアカデミーに参加している皆さ んは、個人個人でいろんな活動をしている。ほんとに、誇らしいなと思いました。 眞竹 :このプログラムの1回目はengawaKYOTO(京都にある電通運営の事業共創スペース)でのリアル開催でしたので、京都を中心とした関西の学生が対象でしたが、昨年オンライン化してから、四国や九州、今年は海外まで広がりましたね。オンライン化ならではのメリットです。では、工藤さんいかがでしょうか? 工藤さん : 私はヤングアカデミーに参加するのが初めてですけど、初日からすぐに思ったのは全員、基礎能力が高く、地頭がいい。学生との懇親会などで話していて、コミュニケーション能力が高いっていうのはもちろんですけど、自分の考えを言語化、構造化して話すというのがとても上手だなと思いました。実際に課題などの評価をする中でも、課題を読み取ってそれを考える力っていうのが高いですね。 眞竹 :ありがとうございます。では、次の質問です。御社は今、学生の皆さんに、どういう企業イメージを持たれていると思いますか? 湊さん :そうですね。やっぱり、広告代理店、CMとか作っている会社、あと、オリンピックやっている会社、というイメージが強いと思います。それ自体は間違ってないですし、弊社のメインのビジネスである事は確かですが、最近はクライアント様の課題がいわゆる広告・プロモーションだけで解決できなくなっている事も増えてきている中で、弊社の社会的役割も変わってきています。 眞竹 :では、御社がどのように変わってきているのか、実際の姿を知らない学生へ、知られていないけれど伝えたいこと、紹介して頂けますか? ― 社会的役割は変わっても、最高の解を提供することは変わらない。 工藤さん :社会的役割が変わってきているというお話ですが、社会ニーズが多様化したり、そもそも従来の尺度では測れなかったりと、ニーズを発見/創造することの重要度がさらに高まっています。そして、そのニーズに応える最高の解を電通は提供する立場にあることは変わらないので、常に最高の解を提供できるように私たちも解のフォーマットにとらわれないようになってきています。従来の広告やプロモーションというフォーマット以外の取り組みとしては、さまざまな事例あるのですが、例えば、 1:DENTSU DESIGN FIRM https://dentsu-design-firm.com/ つたえることから逆算したプロダクト開発をご一緒したり、 2:THE KYOTO https://the.kyoto/article 京都をヒントに文化・アートを学ぶプラットフォームを立ち上げたり、 3:ABC Glamp&Outdoors https://abcgo.co.jp/ テレビ局と一緒に、グランピングで地方創生に取り組む会社をつくったりしています。 眞竹 :では、従来の広告、プロモーション領域に止まらない社会的役割の変化の中で、御社が今後目指していこうとしているところを、教えてください。 工藤さん :目指していこうとしているところは以前から変わっていない気がします。それは、社会やクライアントの課題を発見し、アイデアをもって解決することでちょっと先の未来を引き寄せること。です。ただ、世の中の変化に伴って、サービスをつくったり、事業共創を電通自体ができるように、実現力をさらに強化した電通を目指していく必要はあります。 電通のビジョン&バリュー:an invitation to the never before. https://www.dentsu.co.jp/vision/philosophy.html 眞竹 :では、お二人が現在携わっているもので、従来の広告、プロモーション領域に止まらない事例があれば、教えていただけますか? 湊さん :私と工藤が所属している電通若者研究部(ワカモン)の活動で、それぞれ学生に携わってインターンシップを運営していますので、そちらを紹介します。私の方からは47INTERNSHIP(ヨンナナインターンシップ)のお話をさせて頂きます。 ※「47 INTERNSHIP」 https://47internship.com/ ― 世界のクリエイティブアワードで受賞した47INTERNSHIP。 湊さん :2年目になる2021年も開催しました。昨年、コロナの影響もあり、インターンなどいわゆる就活系のイベントも大きな影響を受けて、就活生が困っているという状況がありました。そこで、逆にコロナだからこそ、新しい就活やその支援の形を作ることができないか、ということをNPO法人のエンカレッジと相談していたところ、これを機会に地方の就活格差に取り組めないか、というアイデアが生まれました。そこから47都道府県から集めた就活生の代表者が参加するインターンシップを開催しました。その取り組みが、様々なところから非常に評価いただきまして、例えば、世界最高峰のクリエイティブアワードのD&ADのブランディング部門にて、2021年最高賞のYellow Pencilを受賞する、ということにもつながりました。 眞竹 :その流れでの2年目。開催にあたって昨年との違いは何か意識されましたか? 湊さん :昨年の経験から、地方の就活格差にこのフレームが有効にワークすることがわかったので、より社会的影響度を高めていこうと考えて企画しました。例えば、これは結構驚かれるのですが、今年は学生から、2000以上のエントリーシートをいただきました。それを受けて、参加される47名以外の方にも希望者を募って、今回の47 INTERNSHIPのエントリーシートの評価基準であったり、これからの時代に求められている人材像はどのようなものか、などをDAY-0という形で協賛企業の皆様にもゲストで参加いただき、全国数百名の学生の皆さんに向けて開催しました。また、エントリーシートにおいて、47都道府県の学生の皆さんに「あなたが解決したい、あなたの身近な課題を教えてください」という質問をしたのですが、それ自体を「47都道府県課題MAP」でビジュアルにして、各地方の皆さんがどういう形で解決していきたいと思っているのかをセットでリリースしました。 「47都道府県課題MAP」 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000085233.html 眞 竹 :ちなみに、どのようなことが地方で学生が感じている課題か、何か傾向は見えたりしたのですか。 湊さん :すごくクリティカルだと思ったのが、コロナになってどんどんネット社会が加速していく中で、地方高齢者のデジタルデバイドを挙げている学生が多かったことですね。そもそもネット化していくのはわかるけど、それについていけない人も結構いて、それが高齢者だったりします。特に高齢者の方がネットの恩恵を受けるべきなのに、それができていないことは、地方社会の大きな構造的な問題だなと改めて感じました。 眞竹 :ありがとうございます。では続いて、工藤さんの取り組みについてお伺いしたいと思います。 ― 「アイデア実現」のための全ての工程を、学生が実体験する。 工藤さん :今年で3年目になる「アイデア実現インターンシップ」についてご紹介します。それまでも電通若者研究部(ワカモン)で電通のインターンシップをプロデュースしていたのですが、私が初めて参加した3年前に新たなフォーマットとして始まったものです。学生とメンターの関係を、先生としてのメンターではなくて、伴走者としてのメンターという立ち位置にしました。学生が主体となって、それこそ、電通の社員が普段やっているような業務の工程を、自分の「ほうっておけないこと」の解決という学生自身のやりたいことを通して実体験をしてもらうことを目的に、アップデートしました。 眞竹 :3年目の今年は、どのような状況ですか? 工藤さん :今まさにクラウドファンディングのCAMPFIREで、11月末まで学生たちが支援を募っている段階です。今年は14人参加してくれたので、14プロジェクトが立ち上がっていますが、もうすでに期間を終えずに目標支援金額を達成しているプロジェクトもあります。 ※「電通ワカモン アイデア実現インターンシップ」 https://camp-fire.jp/curations/dentsu-wakamon 眞竹 :ちなみに、学生の皆さんがどんなプロジェクトを考えたのか、いくつか紹介していただけますでしょうか? 工藤さん :私がメンターをやっていたプロジェクトだと、「Scaping OKAZAKI岡崎プロジェクト」です。キックボードをシェアするサービスで、キックボードで岡崎市の乙川エリアを移動して、「遊び場」化して、その良さに出会って教える、というプロジェクトです。もうCAMPFIREでの目標を達成しているプロジェクトですが、企画した学生が考えたのは、地元岡崎の乙川エリアが車で移動するには道が狭くて移動しにくいし、歩くにしてはちょっと遠い、ということでキックボードに目をつけて、移動そのものも観光にしていく、ということでした。この学生を始め、自分からいろんな人たちや行政などに働きかけを行ってもらうインターンになっています。他にも、「音のない料理教室」。これはイベント系ですけど、参加者同士が声を出さずに意思疎通を図りながら一つの料理を作り上げる、「耳の聴こえる方・聴こえない方が参加できる料理教室」です。すでにこの学生は、インターンに参加する前に一度イベントを開催していて、それをさらにアップデートしたいという思いを持って参加してくれました。 眞竹 : 3年目になり、すでに取り組んでいることがある学生も集まってきているんですね。 工藤さん :参加したメンターの中で、3年目でやっと完成形になってきたかな、という話をしています。学生を集める過程であったり、実際にプロジェクトを考え、立ち上げてもらう期間でであったり、改善できていていると感じています。 眞竹 :お二人はインターンを通じて、学生と企業の接点に携わっていらっしゃいますが、もっとこのようになればいいのに、と感じるところはありますか? 湊さん : 学生の皆さんにとって、企業で働くことにおいて何が大事にされているか、ということを肌で感じる機会があることが重要と思っています。なので、産官学が連携して、実際に働く場としての企業を考える、そういう教育機会を作れれば、就職活動の先行ステップとしてすごくいい機会になるのではないかと思っています。 工藤さん :学生に好きなことを見つけなさい、といってもなかなか難しく、一歩踏み出せない学生がまだまだ多いと思います。大学で学ぶ専門的分野以外でも、興味関心を持てる分野への学びや体験を企業側が提供できるような仕組みがあると面白いのでは、と考えています。 湊さん :就職活動の評価軸が企業側で緩やかに崩れてきている中で、学生側もそれに気づけていないと思っています。例えばeyaで美大の学生が、課題の落とし込みであったり、事業アイデアを作ったりするのがうまいと感じるシーンがあります。作品を作る過程で本質を見極める能力が鍛えられているからだと思うんです。そういう能力は今後企業側にも評価されていくと思うので、そういったことを知れば、きっと学生側の選択肢も広がります。 オンライン取材の様子 左)インタビュアー: 電通 京都BAC engawa young academy 事務局 眞竹広嗣 眞竹 :学生と企業の接点については、今後も改善していくべきポイントがありそうですね。では、そういった中で、電通がeyaに参加される意義やメリットを教えてください。 湊さん :企業紹介の際、広告代理店から、ビジネスをプロデュースする企業へ変化している、という事を、弊社はeyaで学生向けのメッセージとして発信しました。 それは、広告・プロモーションで培ってきた「アイデア」という弊社の強みを活かし、広告・プロモーション領域に留まらずに、クライアント様のビジネスのサポートを行っていきたいという事です。ですが、やはり、このような取り組みはそこまで認知度もなく、事業創造やリーダーシップなどに興味のある学生の皆さんに、弊社の未来の姿を是非知ってもらう機会として活かせればと考えています。 眞竹 :eyaは、異業種による人材育成への取り組みになりますが、そのような取り組みに対してどのようなことを期待されますか? 湊さん :これはメンターとして、学生の皆さんにお伝えしたい事ですが、こういった異業種合同の人材育成の取り組みって、ほんと、大人の社会見学だと思うんですよね。シンプルに、なかなか見えない企業の最先端の事例や、取り組むビジョンに触れる事は、知的好奇心が刺激されますし、楽しい事だと思います。そういった視点でみると、働く事自体がコンテンツになって、それを学生に見てもらうことで、学生の皆さんが働く事にポジティブになってもらう。これが、これからの日本を変えていく一つのカギになるんじゃないか、と思っています。 ― 「今を意味づける力」を身につけてほしい。 眞竹 :では最後に、 eyaの学生たちと接して、感じたこと、期待することは?工藤さんから、お願いします。 工藤さん :最初にお話ししたように、学生の皆さんの考える力がすごく高いなって思っていますが、あくまで提供された課題や自分が見つけた課題に対しての考える力が備わっている、ということだと思います。社会に出た時、その考える力の矛先をもっと広げないと、例えば、スケジューリングだったりとか、タスク管理だったり、人とのコミュニケーションそのものにも電通でいうところのアイデアが必要になります。課題を発見するとか、課題そのものを解決する為に考えるのはもちろんですけど、その矛先をもっといろんなところに向けられるようになって欲しいので、その手助けを、ちょっとの期間でもできればいいなと思っています。 湊さん : 期待することは、ぜひ、小さくまとまらないでほしいという事です。ビジネスをつくる力は勿論重要なのですが、自戒も込めて、それがスモールビジネスの方向にいっちゃう人も、たまにいるんですよね。もちろん、それ自体が悪いコトではないですし、生きていく上で大事な事でもあります。でもそれよりは、ぜひ、日本のこれからを自分が背負うんだ!!という気概を持って、世の中に対して課題感をもって、なるべく大きな理想的な世界観を描くクセをつけてほしい。また、ぜひそんな自分が掲げた世界観が実現できる場所を妥協せずに探して、キャリア設計していってほしいなと感じます。そのためにも、「今を意味付ける力」を身につけてほしいです。メンタープレゼンで1日目に話したことですが、忙しくて目の前の活動を何の為にやっているのか、を見失う時もあると思います。そんな時、立ち止まって、自分のキャリアを考えてみる。そのための材料を提供できる場になればうれしいです。